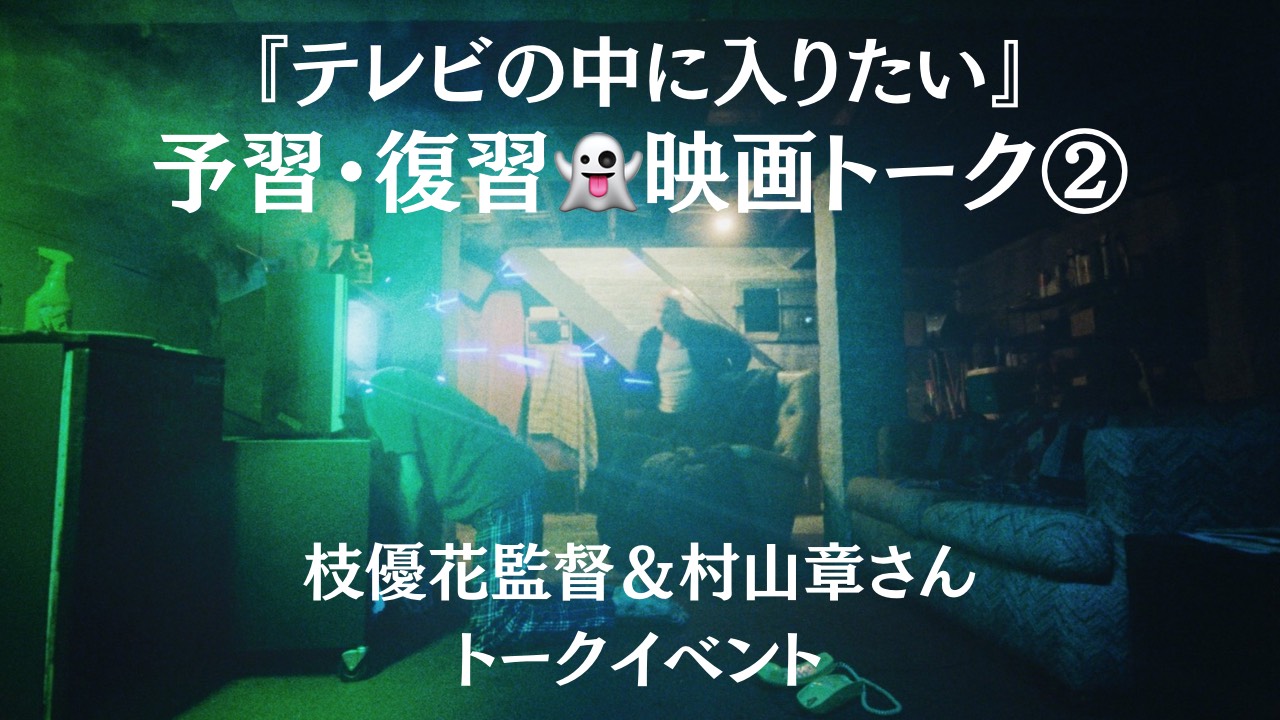
【予習・復習 シネマ談義】枝優花監督×村山章さんトークイベント
先日開催した『テレビの中に入りたい』公開記念トークイベント付き上映、記念すべき第1回に、映画監督・脚本・写真家の枝優花さん、映画ライターの村山章さんが登壇しました。トークの模様をお届けいたします!
🔳枝監督の感想─リアルとフィクションの曖昧さに共感
『ピンク・オペーク』というテレビ番組と、オーウェンがいる現実が入り交ざったようなシーンが多く描かれる本作。枝監督はその境界の曖昧さに共感できると話します。
枝監督「監督をやっていると、現実世界と虚構の世界、その境目がすごく曖昧になることがあるんです。脚本や映像にのめり込んでいると、“こっちの世界とあっちの世界”の区別がつかなくなってくる。撮影中はずっとスタジオにこもって、俗世から切り離された生活をしているんですよ。それが終わると、一気に現実に引き戻されてしんどくなる。しかも脚本を読み込むときは、全部の役を自分に通すので、メンタル的にも負荷がかかります。だから私は瞑想をたまにしていて、それでようやく自分を保てるんです。子どものころも、アニメに没入しすぎて、自分が主人公だと思い込んでテンションや口調が変わったり、日常生活に影響が出ていたことがありました。この映画を観て『うわ、自分だ』と思いましたね」
🔳村山さんの感想─1度目はオーウェン、2度目はマディ
1度目はオンライン、2度目は劇場で観たという村山さん。鑑賞する環境の違いによって、感じたことも変わったそう。
村山さん「オンラインで観たときは『めちゃくちゃ怖い映画だな』って、結構どんよりしたんです。ホラーの感覚というか。でも2回目、劇場で観たら、全然違って。今度はマディ側にぐいぐい引っ張られていってしまった。マディの言っていたことって、本当のことなんじゃない?と思ったんです。たとえば、幼少期のオーウェンが食べている綿あめの色。ルナ・ジュースと色がおんなじで、オーウェンはこの頃からルナ・ジュース漬けにされていたんじゃないかとか、そういう細かい部分に意味があるのかも、“真夜中の国”がもしかしたら現実の比喩なんじゃないかと考えるようになりました」
さらに、青年期のオーウェンの職場環境にも着目。
村山さん「オーウェンが歳をとる一方で、同僚は全然変わらない。あれも“これは現実ではない”っていうサインに見えてきました」
🔳世代による受け止め方と「作り手」「観客」の違い
90年代に青春時代を過ごしたという村山さんは、「『映画に救われる』という実感がある」と言います。
村山さん「でもこの映画はその救いを裏切ってくる。だからこそ、中年以上の映画好きにとっては致死量の刺さり方をするんじゃないかと思います」
一方、90年代にうまれた枝監督は現在31歳。大人になった自分とオーウェンに重なる部分があったそう。
枝監督「若い頃は『こうなりたい』とイメージすると、それが全部叶ってきたんです。イメージできることって、ほぼ全部叶っちゃう。だから『夢は叶わない』って言ってる人を見ると『なんで?』って思ってました。でも最近は、私自身も現実に寄りすぎていたと気づいたんです。ファンタジーみたいなおおきな夢じゃなくて、現実的な目標しか描いていなかった。終盤でオーウェンが「僕は生産的な大人になった」と言いますけど、きっとオーウェンも生産的な大人になりたかったわけではないと思うんです。すごくテレビにあこがれたけど、僕にはなれないと、現実に生きることを決めた人なんだなと。自分を抑え込んでしまった姿がすごく刺さりましたね。逆にマディはずっと夢を描いて、ぶっ飛んでいって、叶えた子なんですよね」
村山さん「いまのお話で思ったのは、メタファーっぽくなりますけど、やっぱり物語を作ったり語ったりする人と観客の違いかもしれないですよね。テレビの中に飛び込むイメージはあっても、作り手に回りたいわけではない、という人もいると思うんです。オーウェンは自分のことを観る側として定義していたのかもしれない」
枝監督「マディとオーウェンの大きな違いですね。オーウェンは憧れはするけど、実際にそこに来いと言われたら違ったのかもしれない」
🔳セクシュアリティとアイデンティティ
本作で扱われるクィアというテーマ。近年、レズビアンやゲイの方をテーマにした作品を扱ってきたという枝監督が思うこととは?
枝監督「当事者の方々と実際に仕事をしたり話を聞いたりする中で思うのは、最終的には『同じ人間だよな』ということです。ただ、社会に受け止められていなかったり、存在を透明化されてしまうことで、本来は失わなくていいはずの自尊心を削がれてしまう。そうすると、自分の可能性を自分で押し込めちゃうんですよね。発言もどこか後ろ向きになるし『どうせ見てもらえてない』と思い込んでしまう。私はその感覚をオーウェンやマディにもすごく感じました」
村山さん「監督自身がノンバイナリーであることも背景にありますよね。自分が“透明化”される経験が、この映画に反映されているんじゃないかと思うんです。僕自身は当事者じゃないので代弁することはできないんですが、監督のインタビューを読むと、すごく理路整然と『自分が何者かに気づく物語なんだ』という話をされていて。作品自体はすごく曖昧で夢のような作りなのに、この部分に関しては監督がめちゃくちゃはっきり言葉にしている。それが印象的ですよね」
村山さんはマディが女性的な装いをすること、オーウェンがピンクの服を着ることが自認や葛藤を象徴しているのではないかと指摘します。
村山さん「イラスト版ポスターのマディって“一番無理してる姿”に見えますよね。女性らしい服装をして、髪の毛も伸ばして染めて、メイクして。本当は女であることに違和感があることは見ていてわかるんですけど、反動的に一番無理している時期なのかなと。オーウェンも、最初からお泊りに行くときに、ピンクの寝袋を持っていく。そのあともずっとピンクの服を着る。でもマディがいなくなったら、地味な色の服しか着なくなってしまうんです」
🔳都会の呪いと田舎の呪い
90年代アメリカの郊外を舞台にした本作。地方出身のふたりは、自身にかかっていた“呪い”を思い出したとか。
村山さん「正直、僕は東京生まれじゃないので、東京出身の人の気持ちってちゃんとはわからないんです。でも、地方出身者って、みんな心のどこかに“呪い”みたいなものを抱えてると思うんですよ。別に地元を嫌いなわけじゃないけど、『ここからは逃れなきゃいけない』みたいな感覚。僕自身もそうでした。枝監督の『少女邂逅』のラストでも、東湖ゆに行くというシーンがありましたけど、まさにそういう逃避や解放のイメージですよね」
枝監督「たしかに。私はこの前、中目黒の川沿いを歩いてたら、20代前半くらいの女の子が小型犬を連れて散歩していたんですよ。昼間から、ダル着姿で、余裕そうに。それを見ていて、ふと『どうやったらこんな人生になるんだ?』って思ったんです。私自身は群馬県出身なので、全然イメージできないんですよ。『群馬出身だから』とか、そういう呪いがいっぱい頭に浮かんじゃう。逆に、それが全然関係ない人は『まあ散歩するよね』って、自然にその人生を歩んでいく。イメージできるかどうか、ですよね。お金持ちの家に生まれた子がまたお金持ちになるのも、結局“自分がそうなるイメージを持てる”から続いていくんだなってすごく思います」
村山さん「もちろん都会には都会の呪いもあるんでしょうけど。作家の山内マリコさんなんかも“地方から都会に出てきた人の呪い”と“都会ならではの呪い”、両方の話を書かれてますけど、この映画はやっぱり地方出身者に強烈に刺さる呪いの物語だと思います」
🔳ラストは希望か、絶望か
「すみません」と謝り続けるオーウェンを映して終わるラストシーンをふたりはどう観たのでしょうか?
村山さん「ラストはね、リアルで救いがないって感じました。でも、それが人生だよなと。枝監督が抱き続けているような勝利のイメージをへし折られる人のほうが多いし、そのなかで折り合いをつけていくようなひとコマに見える。僕はこの映画を人生の話としてとらえているから、あの年齢であの仕事をして家に帰ったら、でっかいテレビと子供と妻がいて『ごめんなさい、ごめんなさい』ってお客さんに謝っている人生って、なんかリアルというか、わかる気がするんですよね」
枝監督「いかようにでも解釈できるので、皆さん捉えたいように捉えたらいいんだと思うんですけど。いまお話していて、オーウェンはずっと外を見ていたなと思って。あこがれとか、諦めのなかで、ラストシーンではじめて自分の中にあるものを見たというのは、希望を感じる変化だなと思います。だけど、演出的にはそこまで明るくも見えなくて、不思議ですよね。やっぱり大なり小なり、自分と向き合うことは苦しいんだと思いました。現実から目を逸らして、外を見たり、誰かのために生きていたほうが楽だけど、オーウェンはその一番苦しいところに切り込んだんだと感じました」