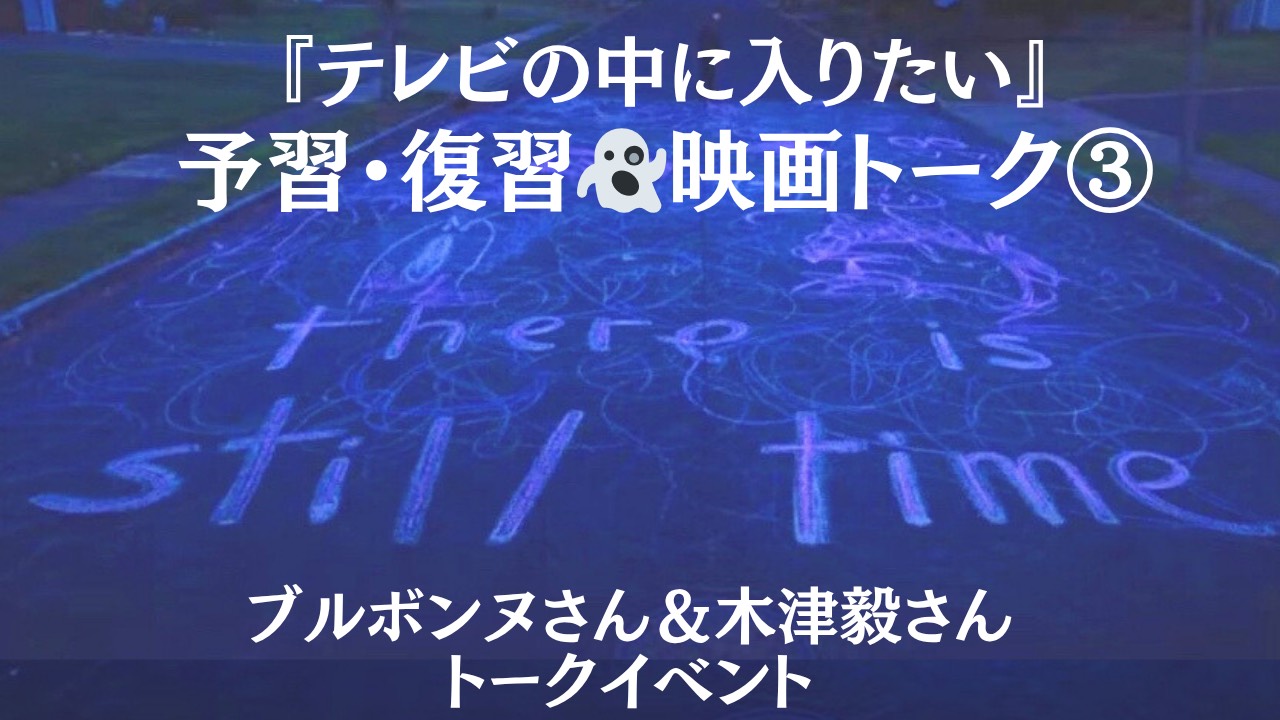
【予習・復習 シネマ談義】ブルボンヌさん×木津毅さんトークイベント
先日開催した『テレビの中に入りたい』公開記念トークイベント付き上映第2回に、ドラッグクイーン・エッセイストのブルボンヌさん、ライター・編集者の木津毅さんが登壇しました。トークの模様をお届けいたします!
🔳映画との出会いと第一印象
木津さん「アメリカでは公開直後からすごい話題になって、ベルリン国際映画祭にも正式出品されましたし、SNSでも大盛り上がりだったんですよ。日本でも公開初日から熱い感想が相次いでますね。僕はアメリカで話題になっている時からずっと楽しみにしていたんです。実際観たら、ただの尖ったクィア映画というだけではなくて、エグいくらい痛切な作品だと思いました」
ブルボンヌさん「実は私、この映画は木津さんに先に勧められて知ったんですよね。木津さんのお話を聞くと、素敵そうだけど、なんだかよくわからないかもと思っていたんです」
木津さん「でもブルボンヌさんにはぜひ観ていただきたいと思っていました」
ブルボンヌさん「そう、それで、冒頭あたりは『やっぱりわからないかも?』と思ったけど、最後まで観て本当に刺さった。かわいくて恐ろしくて、そして自分に重なってしまって、しみすぎる映画。紹介してくれてありがとう」
木津さん「観ていただいてありがとうございます」
🔳監督とキャスト、クィア性
木津さん「監督のジェーン・シェーンブルンさん自身がトランス女性でありノンバイナリー。当事者としてのパーソナルな思いが色濃く反映されていると感じました」
ブルボンヌさん「主演のジャスティス・スミスと、助演のジャック・ヘヴンもクィアを公言してらっしゃるんですよね?」
木津さん「そうなんです。それから、音楽を担当したアーティストもそうですし、本当にたくさんのクィア当事者が関わっている作品なんです。“クィアが作ったクィア映画”と言えると思います」
ブルボンヌさん「クィアって、日本語に訳すと“規範の枠外”というニュアンスですけど、ひと昔前だと差別用語的でしたよね。でも近年、“自分を取り戻す”という文脈で使われている気がします。ジャスティス・スミスくんなんて、『名探偵ピカチュウ』をはじめとする大作にも出ているような俳優だけど、クィアを公言している。若い世代は本当に多様で、それぞれの表現の仕方があるみたいね」
木津さん「そうですね。“クィア”という言葉自体が、今ではフラットにアイデンティティを表現する言葉として広まっています」
🔳90年代のノスタルジーと田舎の呪い
ブルボンヌさん「この映画のルックって完全に90年代の郊外よね。『バフィー 〜恋する十字架〜』やデイヴィッド・リンチのような、みんなが観るわけじゃないけど自分にはやけに刺さる番組があったような、サブカルにハマる若者像を背景に感じました。田舎町では収まりきれないカルチャーに敏感なはぐれ者たちがどう生きるか、そこにみんなシンパシーを感じるんじゃないかな。マディも、最初はすごく仲良くしていた女の子がいたのに、2年後にはひとりになってる。1年間シカトされてる、あいつは夢がチアリーダーになったんだよ、みたいなことを言っていて。すごくわかりやすい、田舎コミュニティのスクールカーストのトップを狙うストレート女になっちゃったってことだと思うんだけど」
木津さん「そうですね。あれは本当に、マディも傷ついたと思うんですよね。本当に大切な親友だと思ってた子が違ったっていう時のショックって、特に十代のころだと、やっぱりすごくくるじゃないですか。僕も経験がありますけど」
ブルボンヌさん「マディの『ここじゃ死んじゃう』ってセリフがすごく象徴的だよね。閉塞感や田舎の人間関係の重さを表しているなと。私は昔から“田舎の呪い”って呼んでるけど、出なければ潰されるし、出ても居場所があるとは限らない。怖いわよね」
🔳オーウェンとマディを分析
ブルボンヌさん「マディは最初から強さがあったと思う。都会に出て、ボーイッシュなレズビアンとして自分を貫いて生きる姿に拍手を送りたい気持ちになりました」
木津さん「ただ、それでも“完全な自由”には届いてないようにも見えました。特に、今のアメリカではクィアへの揺り戻しが強まっていて、都会でも安全とは限らない。そういう現実も反映されているのかなと思いました」
ブルボンヌさん「たしかにね。一方でオーウェンは、2回もマディと交わした脱出の約束をすっぽかす。あれにはちょっと腹が立ちます(笑)。でも同時に、田舎で内に閉じこもってしまう苦しさもすごくわかるのよ。1回目の約束のときに、ほとんど絶交していた子の家に飛び込んで、その子のお母さんに『僕のお父さんに、僕を外出禁止にするように言ってほしい』と伝えるシーンはすごくびっくりしました。こんなことまでして、この子は自分を縛るのかって、つらかった」
木津さん「『ピンク・オペーク』がオーウェンにとっては逃避先でもあり、呪いにも見えて、最後は悪夢的でしたね。テレビが燃える映像とか、ミスター憂鬱のぐにゃぐにゃした動きとか」
ブルボンヌさん「あれ、子供が観たら確実にトラウマよね(笑)。でも、監督が自分の内面の恐怖を形にするとああなるんだろうなと思いました」
🔳ラストシーンと「逃げられない自分」【注:ネタばれあり】
木津さん「オーウェンが最後に自分の中の光を発見するシーン。僕はあそこに希望も見ました。幼いとき、自分の中には何もないと言っていたオーウェンだけど、自分の中にも光があったんだという希望。ラストでやっと発見するけれど、でも同時に“ここで解決というわけじゃない”ということも描いていて。自分からは逃げられない、というメッセージを感じます」
ブルボンヌさん「ほんとそう。田舎から都会に飛び出た私も、ふと鏡を見て『これでよかったのか?』って叫びたくなる瞬間がある。結局はどこにいても地獄で、モヤモヤは一生ついて回るのよね。でも、この作品を通して、自分を押し込め続けた数十年後を見せられたら、ハッとしますよね。本当に、生き方が変わっていくかもしれない」
木津さん「この映画は監督自身の“叫び”に近い作品だと思います。観る人それぞれが自分の人生に重ねていい映画。きっと解釈に正解はないんです。だからぜひ、観終わった後に、どんな部分が刺さったとか、こういうことを描いているんじゃないかと思ったとか、いろんなことを誰かと語り合ってほしいです」
ブルボンヌさん「そうですね。私のなかで、今後の人生でなにかに躓いたとき、ことあるごとに思い出す作品になった気がする。『謝らなくていい』ってマディが最初のころにオーウェンに言ったセリフ、あれが最後とリンクしていて大好きなんです。つい『ごめんなさい』と言ってしまう人に向けて、この映画は“謝らなくていい”と伝えてるんじゃないかしら。こういう作品を観にきてくれるような皆さんにとっても、お守りのような映画になってくれると思います」